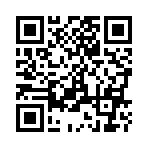2014年09月29日
ハゼ釣り大会
9/28 宍道湖
ハゼ釣り大会に参加してきた。
先週に比べると釣れたよ。
同僚と3時間で71匹。
(うち60匹くらいは自分が釣った)

10匹の総重量で競い、上位5位までが入賞なのだが、私は350g。
親子大会であれば上出来の成績だろう。
ただ、ガチ目の大会。
5位が358g
くーー、8g差で負けた…。
ていうかね、レベル高えわ。
3位までは悔しさを感じる重量だった。
が、この後、2位で390g台。
…これは手ごわい。
運も無ければここまで揃えることはできないだろう。
ここまで400人を超える参加者の上位5位から2位までの差、およそ40g。
…ただ、本当に驚いたが
1位はぶっちぎりの420g台。
いや、430だったか。
2位と30g差!?
2位の重量を聞き、チャンピオンも思わず「あ!やっべえ」と思わなかっただろうか。
こういう数字を聞くと、来年も宍道湖で釣って優勝できる気はしないが、5位入賞は狙えたらなと思う。
70匹にしろ、100匹にしろ、数は揃えることはできると思う。
ただ、重量は難しい。
自分たちも70匹釣って重量がありそうな10匹を選ぶのも迷いに迷ったくらいドングリの背比べ。
同じ宍道湖という環境で育った同級生ハゼたち。
しかも千鳥公園護岸の限られた釣り大会スペースに400人越えの参加者。
よほど成長の早いハゼを限られたスペースで獲らない限り、差はそんなに出辛い。
そしてその時間は3時間というオマケ付き。
70匹釣れると30匹揃えた人には勝てるかもしれない。
だが、70匹釣って優勝重量と70g以上差開くとなるとどーしようもない。
うーん、ハゼ釣り(大会)は奥が深いぜ!
そして今日からハゼ三昧。
71匹の総重量は測ってはいないが、TOP10で350gだから、軽くキロ越えはしていると思われる。
溢れ出るハゼ
しばらくはハゼ三昧…
何事も程よさって必要だね!
2014年09月24日
夜の巨ギスと宍道湖攻略
9/20
ハゼ釣り大会で大量の青虫をもらったもんだから、あまったエサで夜釣りに。
数は出ないものの、やはり良型が釣れる。

キスのアタリの瞬間の瞬発力はすごいね。
ほんとゆるく竿もってると、弾かれるように持って行かれる。
ただ、それ以降は、そんなに大した引きではないんだけど。
最初の一発のアタリで夜釣りだろうが、キスの見分け方はわかってきた。
キス以外は、稚ダイの猛攻。
アタリがあって、ひたすら同じような単調なアタリが続くならマダイで間違いない。

これが一番困る。
単なる雑魚なら良いが、なまじ良い魚の稚魚。
しかもかなりの高確率でハリを呑み込む。
そしてリリースすれば海面をプカプカ…
いっそのこと持って帰ればいいのだろうか?
---
9/21
そして、やはり餌があまるため、翌日また娘と宍道湖リベンジ。

昨日の半分の時間でこれ

やはり、大会中に見つけたやり方で間違いない。

なかなか良い型だよね。
9月ながらハゼもでかくなっているもんだ。
ハゼ釣り大会で大量の青虫をもらったもんだから、あまったエサで夜釣りに。
数は出ないものの、やはり良型が釣れる。
キスのアタリの瞬間の瞬発力はすごいね。
ほんとゆるく竿もってると、弾かれるように持って行かれる。
ただ、それ以降は、そんなに大した引きではないんだけど。
最初の一発のアタリで夜釣りだろうが、キスの見分け方はわかってきた。
キス以外は、稚ダイの猛攻。
アタリがあって、ひたすら同じような単調なアタリが続くならマダイで間違いない。
これが一番困る。
単なる雑魚なら良いが、なまじ良い魚の稚魚。
しかもかなりの高確率でハリを呑み込む。
そしてリリースすれば海面をプカプカ…
いっそのこと持って帰ればいいのだろうか?
---
9/21
そして、やはり餌があまるため、翌日また娘と宍道湖リベンジ。

昨日の半分の時間でこれ

やはり、大会中に見つけたやり方で間違いない。
なかなか良い型だよね。
9月ながらハゼもでかくなっているもんだ。
2014年09月20日
親子ハゼ釣り大会
9/20宍道湖千鳥南公園

娘と親子ハゼ釣り大会に参加してきた。

参加費は100円だったが、飲み物は出るわ、使い切れないほど餌が支給されるわでお得感満載だった。
釣果はこんなもん。

リミットぴったりの10匹揃えたのだが、フタをしてなかったため、2匹が脱走。
まあその二匹がいても、入賞ラインにはいかんのですが。
けど二時間の釣りで宍道湖のハゼ攻略法は見えてきた。
今回は親子大会だったが、来週もう少しガチ目の大会があるからコツは秘密だ!
それなり人より釣ろうと考えると、大会用のコツって言うものが存在する。
そして釣りトーナメントにおいてなぜプラ(プラクティスつまり事前練習)という概念があるのかがわかった。
ハゼ釣りはハゼ釣りでも、その釣り場に行ってみないと、釣り方わかんねえわ。
ていうか、今週一家族10匹釣ったとして100組参加で1000匹のハゼが釣られている。
来週大会出来るほど釣れるのだろうか…
今回の親子大会は面白かったし、来年も参加しよう。
娘が二時間いい子にしてただけでもミラクルだった(笑)
このブログを始めた頃はまだ生まれても無かったわが子だが、成長したな。

そして今大会で使いきれなかった青虫は、今晩投げてこよう。
ワクワク。
娘と親子ハゼ釣り大会に参加してきた。
参加費は100円だったが、飲み物は出るわ、使い切れないほど餌が支給されるわでお得感満載だった。
釣果はこんなもん。
リミットぴったりの10匹揃えたのだが、フタをしてなかったため、2匹が脱走。
まあその二匹がいても、入賞ラインにはいかんのですが。
けど二時間の釣りで宍道湖のハゼ攻略法は見えてきた。
今回は親子大会だったが、来週もう少しガチ目の大会があるからコツは秘密だ!
それなり人より釣ろうと考えると、大会用のコツって言うものが存在する。
そして釣りトーナメントにおいてなぜプラ(プラクティスつまり事前練習)という概念があるのかがわかった。
ハゼ釣りはハゼ釣りでも、その釣り場に行ってみないと、釣り方わかんねえわ。
ていうか、今週一家族10匹釣ったとして100組参加で1000匹のハゼが釣られている。
来週大会出来るほど釣れるのだろうか…
今回の親子大会は面白かったし、来年も参加しよう。
娘が二時間いい子にしてただけでもミラクルだった(笑)
このブログを始めた頃はまだ生まれても無かったわが子だが、成長したな。
そして今大会で使いきれなかった青虫は、今晩投げてこよう。
ワクワク。
2014年09月14日
夜の投げ釣りが面白い
9/12
先日、竿が海に引きずり込まれた時の魚が気になって再度行ってきた。
会社帰りに釣具屋に寄り、100円分だけ青虫を買う。
一本針のちょい投げの場合、100円分で2時間程度は遊べるのだ。
そしてこの釣行で、この歳になって初めて知った。
夜の投げ釣りはかなり面白い
夜釣り(兼餌釣り)と言えば、電子ウキで釣るセイゴ、太刀魚、イカのイメージだったが、
虫餌の投げ釣りも十分成立する。
夜の投げ釣りが面白い理由。
①けっこうアタリが出る

本命ではないにせよ、色んな魚種が果敢に餌にアタックしてくる。
小さいがキジハタ。
もしかすると竿を持って行ったのはキジハタだったか?
②サイズがデカイ。

28㎝のキス釣れました。
これもド派手なアタリ。
もしかして、この前の竿持って行ったのもキスの可能性あるのかもな。
そもそも夜のチョイ投げに行った理由は「島根町某漁港で30㎝を超えるキスが釣れる」という情報があったため。
これ、ほんとだな。
そして、メゴチなどの外道が全く出ないのも夜釣りの強み。
③何が釣れるかわからない

ワニゴチ釣れました。
マゴチかと思いきや、風貌が若干違う!

うーん、竿を持って行ったのはコチの可能性も??
でも、この魚は居食いでした。
コンコンあたりが出ただけで、あとはじーっとしてた。
ルアーで散々やっても釣れないのに、虫餌で釣れることもあるのね…。
というわけで、夜のチョイ投げはハマる。
また時間を見つけて行きたい。
そして、キスをとりこんでいる時に一瞬キスがのたうち回るような手ごたえがあったのだが、家でよく見ると噛み跡があった。

何が噛んだんだ?
ヒラメ?ハタ?
夜の海は想像以上に魚が動いている。
これは面白い。
タコの次は、夜の投げ釣りにハマるのか?俺。
先日、竿が海に引きずり込まれた時の魚が気になって再度行ってきた。
会社帰りに釣具屋に寄り、100円分だけ青虫を買う。
一本針のちょい投げの場合、100円分で2時間程度は遊べるのだ。
そしてこの釣行で、この歳になって初めて知った。
夜の投げ釣りはかなり面白い
夜釣り(兼餌釣り)と言えば、電子ウキで釣るセイゴ、太刀魚、イカのイメージだったが、
虫餌の投げ釣りも十分成立する。
夜の投げ釣りが面白い理由。
①けっこうアタリが出る
本命ではないにせよ、色んな魚種が果敢に餌にアタックしてくる。
小さいがキジハタ。
もしかすると竿を持って行ったのはキジハタだったか?
②サイズがデカイ。
28㎝のキス釣れました。
これもド派手なアタリ。
もしかして、この前の竿持って行ったのもキスの可能性あるのかもな。
そもそも夜のチョイ投げに行った理由は「島根町某漁港で30㎝を超えるキスが釣れる」という情報があったため。
これ、ほんとだな。
そして、メゴチなどの外道が全く出ないのも夜釣りの強み。
③何が釣れるかわからない
ワニゴチ釣れました。
マゴチかと思いきや、風貌が若干違う!
うーん、竿を持って行ったのはコチの可能性も??
でも、この魚は居食いでした。
コンコンあたりが出ただけで、あとはじーっとしてた。
ルアーで散々やっても釣れないのに、虫餌で釣れることもあるのね…。
というわけで、夜のチョイ投げはハマる。
また時間を見つけて行きたい。
そして、キスをとりこんでいる時に一瞬キスがのたうち回るような手ごたえがあったのだが、家でよく見ると噛み跡があった。
何が噛んだんだ?
ヒラメ?ハタ?
夜の海は想像以上に魚が動いている。
これは面白い。
タコの次は、夜の投げ釣りにハマるのか?俺。
2014年09月10日
ジュニオール・ドス・カニヤス
人生初、夜のチョイ投げをしました。
油断していて、置き竿にしているほんの数秒の間に、竿が海の中に引きずり込まれました。
あの魚は何だったんだろう?
aiatosanです。
ちなみに竿が海中に持って行かれるのは2回目。
一回目は、小学生の時に30㎝に満たないコトヒキに持っていかれました。
コトヒキって相当引くからね。
これは幸い回収できたから魚がわかった。
今回は慌てて、予備竿にジグヘッド付けて竿は回収したんだけどハリスは切られちまった。
途中まで魚付いてたんだけどね。
ちなみに餌は青虫。
シーバスか、チヌかなあ…
こういうのが一番悔やまれる。
とある情報から、夜釣りでも大型キスが釣れると聞きまして。
週末のハゼ釣りで余った青虫持って行ったんですわ。
やってみるとキスこそ釣れなかったものの、マダイやアコウが釣れ、アタリも頻繁にあって想像以上に面白かった。
また行こう。
やっぱ餌釣りって良いわ。
めっちゃアタリあるもんな。
---
さて、皆さんがお待ちかねのタコ情報ですが、不用意な釣り方で初代カニヤス↓は殉職。

仕方なし、二代目を買いに行ったのだが、この白のカニが売り切れ…
なぜだ。
これはブログの影響なのか…
と妄想に浸ったが、無いものは仕方ない。
リアルカニカラーで揃えた。

二代目、カニヤス。
ジュニオール・ドス・カニヤスを操作していると、見える範囲にタコが居たので動画で撮ってみました。
安デジカメのビデオモードなので映像の悪さはご承知おきください。
ただ、よく見ていただくとタコの姿がわかるはずです。
ちなみにラインの細いリール使ってたので、釣ってはいません。
この後、タコ用のリールに替えて獲りました。

もう、正式に数えてないが、今季タコに目覚めて20ハイ以上は釣っている。
ウナギ同様、一通り極めた感があるので今月からは本格的に日本海のアオリイカへとシフトチェンジしたい。
油断していて、置き竿にしているほんの数秒の間に、竿が海の中に引きずり込まれました。
あの魚は何だったんだろう?
aiatosanです。
ちなみに竿が海中に持って行かれるのは2回目。
一回目は、小学生の時に30㎝に満たないコトヒキに持っていかれました。
コトヒキって相当引くからね。
これは幸い回収できたから魚がわかった。
今回は慌てて、予備竿にジグヘッド付けて竿は回収したんだけどハリスは切られちまった。
途中まで魚付いてたんだけどね。
ちなみに餌は青虫。
シーバスか、チヌかなあ…
こういうのが一番悔やまれる。
とある情報から、夜釣りでも大型キスが釣れると聞きまして。
週末のハゼ釣りで余った青虫持って行ったんですわ。
やってみるとキスこそ釣れなかったものの、マダイやアコウが釣れ、アタリも頻繁にあって想像以上に面白かった。
また行こう。
やっぱ餌釣りって良いわ。
めっちゃアタリあるもんな。
---
さて、皆さんがお待ちかねのタコ情報ですが、不用意な釣り方で初代カニヤス↓は殉職。
仕方なし、二代目を買いに行ったのだが、この白のカニが売り切れ…
なぜだ。
これはブログの影響なのか…
と妄想に浸ったが、無いものは仕方ない。
リアルカニカラーで揃えた。
二代目、カニヤス。
ジュニオール・ドス・カニヤスを操作していると、見える範囲にタコが居たので動画で撮ってみました。
安デジカメのビデオモードなので映像の悪さはご承知おきください。
ただ、よく見ていただくとタコの姿がわかるはずです。
ちなみにラインの細いリール使ってたので、釣ってはいません。
この後、タコ用のリールに替えて獲りました。
もう、正式に数えてないが、今季タコに目覚めて20ハイ以上は釣っている。
ウナギ同様、一通り極めた感があるので今月からは本格的に日本海のアオリイカへとシフトチェンジしたい。
2014年09月03日
Vフラットと蛸
ついにやったぜ。

メガバスのVフラットにYO-ZURIのタコベイトを被せたルアーでタコゲット。

抱かせたことはあったのだが、フッキングから陸揚げまでは初。
まさか最後にナマズを釣ったルアーでタコを釣るとは想像だにしなかった。

しかし、こんな快挙な日に限ってデジカメ忘れてるっていうね。
携帯カメラも捨てたもんじゃないが、夜釣りには向かない。
タコ専門のタコスピンもあるけど、バスルアーの性能の良さはさすが。
あとフッキングだけ克服できれば、第二の蛸ラバになれるだろうに。
メガバスのVフラットにYO-ZURIのタコベイトを被せたルアーでタコゲット。

抱かせたことはあったのだが、フッキングから陸揚げまでは初。
まさか最後にナマズを釣ったルアーでタコを釣るとは想像だにしなかった。

しかし、こんな快挙な日に限ってデジカメ忘れてるっていうね。
携帯カメラも捨てたもんじゃないが、夜釣りには向かない。
タコ専門のタコスピンもあるけど、バスルアーの性能の良さはさすが。
あとフッキングだけ克服できれば、第二の蛸ラバになれるだろうに。
2014年09月02日
NHKの二宮アナがあり得ない
8/31 NHKでやってた
さかなクンのギョギョ魚発見~東京湾スペシャル~
という番組があったからたまたま見てた。
東京湾に生息する魚の魚種は700種類。
そのくだりで、この魚は何でしょう?
と、東京湾に生息する魚のイラストを見てその魚の名前を答えるクイズをやっていた。
まずは男の子の子どもタレント、
ホウボウを指されて
「ホウボウ!」
と答える。
これは見事!!
同じ年の(大体小6くらい?)の同世代に答えさせても正答率は10%に満たないのではないだろうか。
もしかしたら、自分が出演する番組の内容を理解して予め予習してきたのかもしれない。
それはそれで素晴らしいプロ根性だ。賞賛に値する。
次に二宮直輝アナウンサー
さかなクンが指した魚は
「マゴチ」
マゴチはホウボウ並みの認知度だと思うが、正直、一般人には難しい問題だ。
そこでさかなクンが「夏のフグと呼ばれている魚」
さらに「天婦羅で旨い!」
と矢継ぎ早にヒントを与えるが、天下のNHKアナが3の倍数を叫ぶ世界のナベアツ並みに絶叫した答えは
「カサゴ!!」
いやいや、あり得んやろ。
サブパーソナリティの大沢あかねさんに
「コチ!」
と答えられる始末。
確かに「マゴチ」と答えられると「あれ、この人釣りやってんの?」と思ってしまう問題だ。
けれども「カサゴ」と絶叫しない分別はあってもらいたいものだ。
天下のNHKならば。
まあ、これが「ハゼ」とか言ってると、「ああ、この人やるじゃん」くらいなのだが。
この珍回答によって自分が「コチ」が何であるかも「カサゴ」が赤い体色をした魚であることすら、わからないことを知らしめてしまった。
カサゴとか料理店で出されたことないのかな。
NHKアナウンサーならば毎日全国チェーン店の牛丼ばっかり食っているわけじゃないだろうに。
そもそもNHKアナは自局の番組を見ないのだろうか?
ダーウィンが来た
とか。残念である。
しかし他山の石。
自分も他業種の人にこんな恥ずかしい受け答えしてるのかなと思うと最低限の勉強って大事だなと。
しかし年間365日の内、200日くらいを水辺で過ごす人間と、2日くらいの人とでは、共通点は同じ地球の空気を吸っていることくらいしかないのかもしれない。
自分が近年一番衝撃を受けたツッコミは、
旅行で訪れた伊豆の稲取で夜釣りをしていた時だ、まったく自然音痴な親子3人連れがやってきて母親が発した言葉が
「こんな夜なのに、魚って目が見えるんですか?」
…何と答えて良いかわからなかったが
すぐさま「何が釣れるんですか」
と聞かれたため
「さあ、自分も観光客なんで」
と正直且つ無関心な回答をしてしまった。
どう説明しても、理解できるはずがないからだ。
「こんな暗くて魚って目が見えるんですか?」
と聞いて
「ああ、そうか!夜だって事を忘れていた。魚も眠っているのに釣りをするのはなんて愚かなことなんだ!」
と言うとでも思ったのだろうか。
逆に、闇のサバンナで獲物を狙うライオンや、ライトに照らされ不気味に光るハイエナの映像を見たことがないのだろうか?
真夜中に操業するイカ釣り漁船の映像を見たことがないのだろうか?
自然界のあらゆる生物は人間の視力と同じ程度と思っているのだろうか?
そう思っている根拠は何なんだろう。
どう説明すれば、わかってくれるのだろうか。
そもそも、質問するからには知ろうという意欲はあったのだろうか。
また、この類の衝撃を受けたのが、ジブリの「崖の上のポニョ」
この映画のあるシーンで違和感を覚えた方はいないだろうか?
主人公のそうすけが海で死にかけたポニョを発見したシーン。
(少なくともここまでのストーリーでポニョは海水に住んでいる魚というのが前提となっている)
そうすけがバケツに水道水をガバガバ入れて(それも真剣な表情で)、その中にポニョを放り込むとポニョが元気に泳ぎ出すのだ。
アイロニックな釣り人はこんな描写に目ざとい。
それ見た瞬間に
「ああ、これよほど自然に関心の無い人間が描いたんだな」
と一瞬で悟ってしまう。
悪いが、これは成人の釣り人だから気がつくというレベルではない。
その昔、まだ自分が幼稚園児の時、父親に連れて行ってもらった海岸で「持って帰るな」と固く諭されていた岩ガニをこっそり家に持ち帰ったことがあった。
そして虫かごに入れ、水道水を入れておいたら、すぐ死んだ。
それで気がついた。
海の生き物は塩水じゃないと生きられないのだと。
子どもは単純だ。
その次に持ち帰った時は、水道水に塩を入れ、カニを入れた。
するとこれもすぐ死んだ。
海水は食塩では作れないのだ。
詳しい理屈はわからなくても小学校入学前の自分でもそれくらいわかった。
気がつくのは早かったかもしれないが、海辺に暮らす子どもやある程度の歳の子ならわかることだ。
これすら気がつかないまま大人になって、周りに向かって情報を発信する人間がいる。
あなたはある分野において自分の幼稚園の知識に追いついてない大人が作ったアニメ、作品を見たいと思うだろうか?
少なくとも私は見たいと思わない。
何でも広く浅く(できれば少々深く)知るということは必要だ。
世間一般に常識レベルの自然に疎い人というのは少なからず居る。
そういう人に限って、海や川をきれいに。自然を大切に。地方の魚は安くておいしい。という。
自分の家の前の川にウナギがいることもアユが遡上していることも知らず(関心を持たず)、
川に捨てられたゴミだけ見つけて清掃を行う善人を私はどこか残念に思う。
ゴミ拾いという行為はとても素晴らしいことであることは絶対に間違いない。
けど何かが違う。
違うんだよ。ちょっと
さかなクンのギョギョ魚発見~東京湾スペシャル~
という番組があったからたまたま見てた。
東京湾に生息する魚の魚種は700種類。
そのくだりで、この魚は何でしょう?
と、東京湾に生息する魚のイラストを見てその魚の名前を答えるクイズをやっていた。
まずは男の子の子どもタレント、
ホウボウを指されて
「ホウボウ!」
と答える。
これは見事!!
同じ年の(大体小6くらい?)の同世代に答えさせても正答率は10%に満たないのではないだろうか。
もしかしたら、自分が出演する番組の内容を理解して予め予習してきたのかもしれない。
それはそれで素晴らしいプロ根性だ。賞賛に値する。
次に二宮直輝アナウンサー
さかなクンが指した魚は
「マゴチ」
マゴチはホウボウ並みの認知度だと思うが、正直、一般人には難しい問題だ。
そこでさかなクンが「夏のフグと呼ばれている魚」
さらに「天婦羅で旨い!」
と矢継ぎ早にヒントを与えるが、天下のNHKアナが3の倍数を叫ぶ世界のナベアツ並みに絶叫した答えは
「カサゴ!!」
いやいや、あり得んやろ。
サブパーソナリティの大沢あかねさんに
「コチ!」
と答えられる始末。
確かに「マゴチ」と答えられると「あれ、この人釣りやってんの?」と思ってしまう問題だ。
けれども「カサゴ」と絶叫しない分別はあってもらいたいものだ。
天下のNHKならば。
まあ、これが「ハゼ」とか言ってると、「ああ、この人やるじゃん」くらいなのだが。
この珍回答によって自分が「コチ」が何であるかも「カサゴ」が赤い体色をした魚であることすら、わからないことを知らしめてしまった。
カサゴとか料理店で出されたことないのかな。
NHKアナウンサーならば毎日全国チェーン店の牛丼ばっかり食っているわけじゃないだろうに。
そもそもNHKアナは自局の番組を見ないのだろうか?
ダーウィンが来た
とか。残念である。
しかし他山の石。
自分も他業種の人にこんな恥ずかしい受け答えしてるのかなと思うと最低限の勉強って大事だなと。
しかし年間365日の内、200日くらいを水辺で過ごす人間と、2日くらいの人とでは、共通点は同じ地球の空気を吸っていることくらいしかないのかもしれない。
自分が近年一番衝撃を受けたツッコミは、
旅行で訪れた伊豆の稲取で夜釣りをしていた時だ、まったく自然音痴な親子3人連れがやってきて母親が発した言葉が
「こんな夜なのに、魚って目が見えるんですか?」
…何と答えて良いかわからなかったが
すぐさま「何が釣れるんですか」
と聞かれたため
「さあ、自分も観光客なんで」
と正直且つ無関心な回答をしてしまった。
どう説明しても、理解できるはずがないからだ。
「こんな暗くて魚って目が見えるんですか?」
と聞いて
「ああ、そうか!夜だって事を忘れていた。魚も眠っているのに釣りをするのはなんて愚かなことなんだ!」
と言うとでも思ったのだろうか。
逆に、闇のサバンナで獲物を狙うライオンや、ライトに照らされ不気味に光るハイエナの映像を見たことがないのだろうか?
真夜中に操業するイカ釣り漁船の映像を見たことがないのだろうか?
自然界のあらゆる生物は人間の視力と同じ程度と思っているのだろうか?
そう思っている根拠は何なんだろう。
どう説明すれば、わかってくれるのだろうか。
そもそも、質問するからには知ろうという意欲はあったのだろうか。
また、この類の衝撃を受けたのが、ジブリの「崖の上のポニョ」
この映画のあるシーンで違和感を覚えた方はいないだろうか?
主人公のそうすけが海で死にかけたポニョを発見したシーン。
(少なくともここまでのストーリーでポニョは海水に住んでいる魚というのが前提となっている)
そうすけがバケツに水道水をガバガバ入れて(それも真剣な表情で)、その中にポニョを放り込むとポニョが元気に泳ぎ出すのだ。
アイロニックな釣り人はこんな描写に目ざとい。
それ見た瞬間に
「ああ、これよほど自然に関心の無い人間が描いたんだな」
と一瞬で悟ってしまう。
悪いが、これは成人の釣り人だから気がつくというレベルではない。
その昔、まだ自分が幼稚園児の時、父親に連れて行ってもらった海岸で「持って帰るな」と固く諭されていた岩ガニをこっそり家に持ち帰ったことがあった。
そして虫かごに入れ、水道水を入れておいたら、すぐ死んだ。
それで気がついた。
海の生き物は塩水じゃないと生きられないのだと。
子どもは単純だ。
その次に持ち帰った時は、水道水に塩を入れ、カニを入れた。
するとこれもすぐ死んだ。
海水は食塩では作れないのだ。
詳しい理屈はわからなくても小学校入学前の自分でもそれくらいわかった。
気がつくのは早かったかもしれないが、海辺に暮らす子どもやある程度の歳の子ならわかることだ。
これすら気がつかないまま大人になって、周りに向かって情報を発信する人間がいる。
あなたはある分野において自分の幼稚園の知識に追いついてない大人が作ったアニメ、作品を見たいと思うだろうか?
少なくとも私は見たいと思わない。
何でも広く浅く(できれば少々深く)知るということは必要だ。
世間一般に常識レベルの自然に疎い人というのは少なからず居る。
そういう人に限って、海や川をきれいに。自然を大切に。地方の魚は安くておいしい。という。
自分の家の前の川にウナギがいることもアユが遡上していることも知らず(関心を持たず)、
川に捨てられたゴミだけ見つけて清掃を行う善人を私はどこか残念に思う。
ゴミ拾いという行為はとても素晴らしいことであることは絶対に間違いない。
けど何かが違う。
違うんだよ。ちょっと